若い頃、猛烈に仕事をした。家に帰ってやることといえば、着替えと、少しの睡眠と、たまの慌ただしい食事。
妻や子供との会話も、一週間で数えるほど。育児も家事も妻に任せきり。子供の塾や、新しい家電にも興味がなかった。ほとんどの時間を、職場か、仕事関係の知人と過ごしていた。
そういう時代だった。みんなそうしている、と思っていた。
妻が二人の子供とともに出ていったのは、仕事が猛烈に忙しい時期だった。
会社に二日間泊まり込んで仕事をし、着替えを取りに帰ったときに、書き置きを見つけた。
それを見た瞬間には、特になんの感情も湧かなかったように思う。
「もう少しでこのプロジェクトも片がつく。あと少しがんばろう。終わったら少し旅行でもしてリフレッシュしよう」と考え、着替えを持ってまた仕事場に戻った。

あれから十数年が経つ。
妻や子は、どうしているだろうか。
そんなことを思いながら、安居酒屋のカウンターで、瓶ビールをグラスに注ぐ。
となりに、私と同じくらいの年の男性が座った。
しばらく無言で飲んだあと、ふいにその男がつぶやいた。
「妻がね、こないだ亡くなったんですよ」
独り言かと思ったが、どうやら私に向けて話しかけたらしい。
「妻を愛していました、とても」
今度ははっきりと、私の方を向いて言った。
「それはお気の毒でした」
私が応えると、彼は語り始めた。

彼が彼の妻と出会ったのは、43歳の秋だった。
妻に出会うまでの彼は、仕事が楽しく充実していて、時間のほとんどを仕事に費やしていた。
何人かのガールフレンドはいたものの、結婚し自分の自由がなくなるのは嫌だと考えており、特定の女性と仲が深くなって結婚の話が出ると少しずつフェードアウトする、という気楽な独り身を謳歌していた。当時流行った「独身貴族」という言葉が当てはまる。
そんな彼がなぜ、特定の女性に惹かれ結婚を決断したのかはわからない。
「そういうものである」という他ない。
とにかく彼は一人の女性に強烈に惹かれ、それまでの自分の考え方を改め、結婚した。
彼の妻は離婚を経験していた。
そして結婚というものにナーバスになっていた。
「もう失敗したくない」が彼女の口癖だった。
そういう事もあって、彼はより一層自分を奮い立たせた。
「これ以上彼女を苦しませてはならない」と思った。
彼と妻の結婚生活は順調だった。
二人の間に子供はできなかったが、それでも楽しかった。
彼は職場を変え、ワークライフバランスがとれる会社に転職した。
平日は遅くとも18:00には家に帰り、家で食事を共にした。
夜の盛り場にも行かなくなり、休日はほとんどの時間を良き夫としてショッピングセンターや公園で過ごした。
収入や交友関係は大きく減ったが、彼は満ち足りていた。
彼の世界は、彼の妻との世界がすべてになりつつあったが、彼は幸福だった。
それは彼の妻の望みだったし、彼はほんとうに妻が好きだったから。
そう、実は彼と妻の間に子どもはできなかったのだが、彼らには子どもがいた。
妻の連れ子である。
正直言うと、彼と子どもたちの間には、ギクシャクしたものがあった。
「お父さん」と呼ばれたことは一度もない。
彼は、心の底から子どもたちを愛することができなかったかもしれないが、できる限りの努力をした。
愛する妻のために、子どもたちも愛そう、と思った。
子どもたちは自分に対してそう思ってくれないかもしれないが、それは仕方のないことだ。
ただ、子どもたちに嫉妬している自分を感じるときは、さすがに辛かった。
妻は自分以上に子どもたちを愛している、そう感じることがよくあった。
そしてそれは年々強くなっていった。
それも仕方のないことだ、と彼は慮った。
「これまでのガールフレンドたちに散々冷たいことをしてきた私が、
妻と出会って本当の愛を知った。
愛とは、その人のすべてを愛することだ。
その人が愛するものや、その人を愛するもの、その人を取り巻くすべてを。」
と、当時の彼は、何度も自分に言い聞かせた。
妻は彼に、たびたび感謝の言葉を述べた。
「ありがとう。私と、子どもたちを、愛してくれて」
と、何度か言われ、その度に彼は涙ぐんだ。
「この人と結婚してよかった」と思った。
そして「こちらこそありがとう」と伝えた。
子どもたちは成長し、彼と妻は老いていく。
時が流れ、子どもたちは東京と名古屋でそれぞれ就職し、そこで家庭を築いていた。
年に1回は帰省し、可愛い孫の顔を見せてくれる。
彼も妻も、その帰省を毎年一番の楽しみにしている。
やがて妻は、病に冒された。
闘病生活は2年半続いた。
都会で頑張っている子どもたちに迷惑はかけられないという想い、
そして、妻を独り占めできる、という感情もあって、
彼は仕事を辞め、看病に専念した。
自分を捨て、一人で妻に寄り添う、と決めた。
妻は何度も彼に「ありがとう」と言った。
妻の最期が近づいたとき、彼にもよくその事がわかった。
怖く悲しかったが、「妻の最期を看取れる」という達成感があったのも事実だ。
彼は病院で寝泊まりした。
妻の意識は混濁し、枕元で額の汗を拭う彼のことも分からなくなった。
ときには乱暴に「やめてよ!」と手を払いのけられてしまうこともあった。
でも彼は、妻との残り少ない時間を、大切にしようと思った。
一秒一秒が愛おしかった。
それは、突然やってきた。
ある夜、枕元でうとうとしていた彼が目を覚ますと、妻がしっかりと目を開けていた。
目は病室の天井を見据えている。
「ごめんなさい、そうたさん、さようなら」
妻は言った。そしてゆっくりと目を閉じ、二度と開けなかった。

そこで言葉が止まったので、顔を向けると、彼は肩を震わせていた。
それまで幸せそうに語っていた彼の声は、正反対の色に包まれた。
「私はそこで、わからなくなりました。
私の名前は、そうたではない。子どもたちの名前を違う」
「でも..」
私が言いかけると、彼はその言葉を遮ってまくし立てた。
「私は妻から愛されていなかったのかもしれない。私が愛していたからといって、妻が私を愛する道理はない。
子どもたちの学費や妻の治療費で、お金もぜんぜんない。なにもない。
なにも考えてなかったからね。その時の幸せだけを考えて生きてきたんだ。
恥ずかしいけれど、お金はなくていい、愛だけあればいいと思ってた。
そしていま、私には何も残ってない」
彼はカウンターに突っ伏してしまった。
その時、私の携帯が鳴った。メールが来ている。
「きょう、予定通りいつもの部屋で9時に待ってます。早く聡太さんに会いたいよ☆」
もうこんな時間か。
いま私のまわりにいる女は、カネ目当てだろうか。
そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
結局そんな問いに答えがないことを私は知ってる。
「まあ、元気をだしてください。お先に失礼」
そう言って肩を叩き、店を出てタクシーを拾う。
(2,869字)
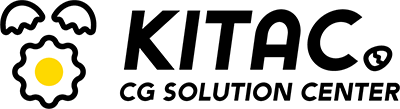

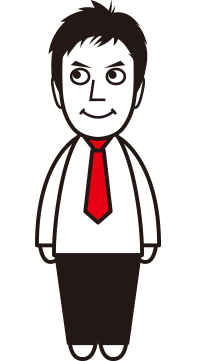
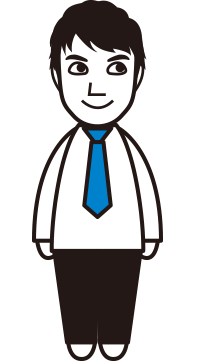
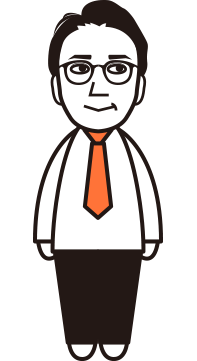
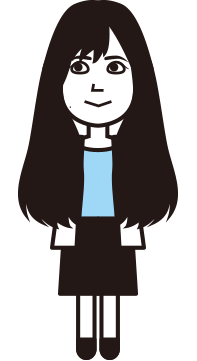
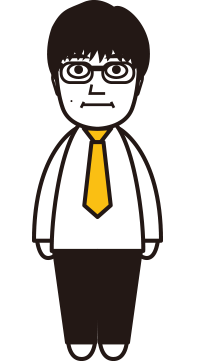
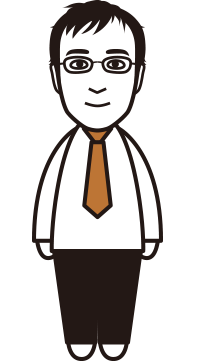

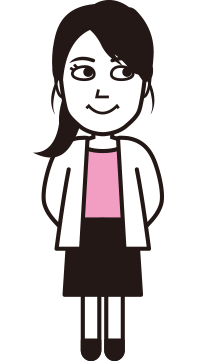
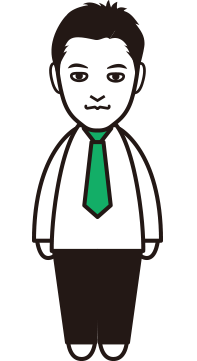
よろしければどうかご感想を!
※コメントは、サイト管理者による承認後、ページに表示されます。